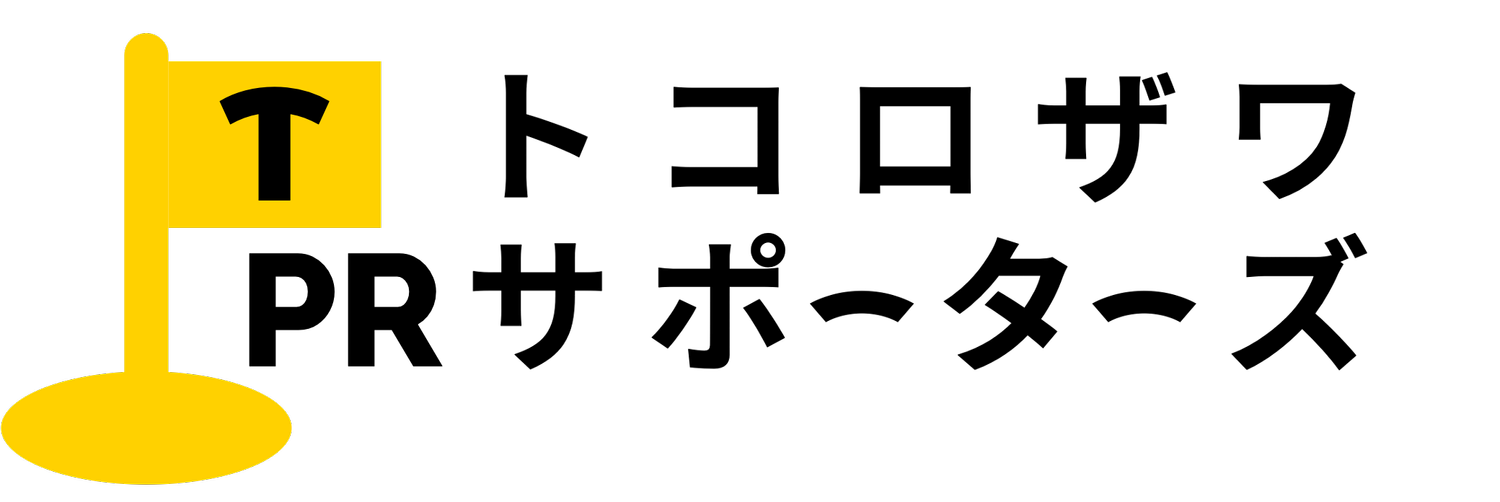PRって広告?マーケって何?ブランディングとは?!【PR編】
こんにちは。所沢PRサポーターズ(略称:TPRS)のグッチです。
TPRSを立ち上げてみたものの、市内の様々な事業者さんと話をするなかで、ふと「そもそもPRってどんなことするの?」「マーケティングって何?」「ブランディングってロゴ作ること?」といった疑問やモヤモヤがあることに気付きました。
モノを作る・営業(販売)をする・経理をする・・・といった職種のなかでも、PR(広報)や広告(宣伝)、マーケティングなどは企業によっても内容が多岐にわたり、境目が曖昧だたり、融合しているケースも多いので「よく分からない」分野なのかもしれません。
そこで、この機会に自分でもあらためてこの分野を整理し、自分なりにまとめてみました。
1. PRとは
PRは「Public Relations(パブリック・リレーションズ)」の略になります。
パブリックとは、一般的には「公共」とか「社会」という意味ですよね。企業におけるPRの役割は、その事業者と関係のある人たちを中心としたパブリックと良好な関係を構築するための活動をします。
2. PRの定義
国際PR協会(IPRA)では、「信頼のおける、倫理的なコミュニケーション手法を通し、組織と組織をとりまくパブリックとの間に、関係と利益を築くため、意思決定の管理を実践すること」と定義されていますが、簡単にいうと、「組織が、ステークホルダー(*1)をはじめとした社会に向け、情報を発信・管理すること」とあります。
ここで「管理ってなんだろう?」と思われた方がいらっしゃるかもしれません。日本パブリックリレーションズ協会では「組織がステークホルダーと双方向のコミュニケーションを行い、組織内に情報をフィードバックして自己修正を図りつつ、良い関係を構築し、継続していくマネジメント」をPRの定義としていますが、解釈すると、「社会との良好な関係構築のために一方通行ではないコミュニケーションをとりながら維持・改善をすること」が管理に該当するのかなと個人的に理解しています。
*1:「ステークホルダー」従業員や顧客、取引先などの利害関係者のこと
『PR戦略入門』著者の加固三郎氏によれば、「PRとは、公衆の理解と支持を得るために、企業または組織体が、自己の目指す方向と誠意を、あらゆる表現手段を通じて伝え、〜(中略)〜それを実行する活動を伴わなければならない。」とあります。
さらに平たくいうと、「自社を含む様々なメディアに露出・情報発信して社会の理解を得るための活動」になります。
参考:加固三郎『PR戦略入門』ダイヤモンド社、1969年。
3. PR発展の背景
PRは、元々PR先進国のアメリカなどが第一次世界大戦時のプロバガンダに使用した戦略的な活動の一つだったものが、戦後にビジネスでも活用され発展してきた背景があります。
ちなみに、「自己PR」という慣用句があるように、「PR=宣伝」とイメージされている方は多いかもしれません(「ピーアール」と「アピール」が似通っているのも影響しているかも?!)。私が企業勤めをしていた頃は、「広報・宣伝部」「プロモーショングループ」「マーケティングPR」などなど、部署の名称のバリエーションが多く、転職先で求められる「PR」に違いがあったので、PRパーソンでもそれぞれに解釈が異なると思います。
元々、戦時中にPRがプロバガンダで利用された活動だったことを踏まえると、「PR=宣伝」とイメージするのは自然なことかもしれませんが、現代においては「宣伝」は「広告」とほぼ同義となります。そしてその情報の受け手は発信側(事業者)が行動を促したい相手である消費者がメインとなります。
PRは受け手が”社会”という広く、とても曖昧な対象ではありますが、主なターゲットはメディアを含むステークホルダーになり、「客観的且つ正確な情報を求められる」PRの立場上、中立性が高いポジションとなります。
4. PRと広報の違い
さらに、「PR」と「広報」という言葉の違いにも注目してみたいと思います。
結論からいうと、「PR」と「広報」は基本的には同義です。ただ、PRという概念がアメリカから導入された戦後の日本で的確な和訳は難しかったようです。結局「広報」と和訳されて今に至りますが、文字だけを解釈すると、「広報」は一方的なコミュニケーションが強いため、今も区別して使用している企業はあります。
さらに、「PR」は先述の「宣伝」という意味合いで使用しているところもあるため非常に複雑です。この言葉の意味の複雑さや曖昧さが「PRって何?」「PRプランナーって(怪しい…)」に繋がっているのかもしれません。
5. PR記事はPRにあらず
ちなみに皆さんは新聞や雑誌の「PR記事」という表記を見たことはありませんか?広告とは雰囲気の違う、しっかりと「読み物」風になっていますが、実はこれ、「広告」なんです。パッと目を引くような広告とは異なり、インタビュー形式になっているなど「記事」のような見せ方の広告は「記事広告」または「PR記事」と呼ばれています。PRはメディアにとりあげてもらうにあたってお金は発生しませんが、広告は有料です。なぜなら”編集権”が広告主(事業者)にあるからです。でも、「PR記事」はPRと記載されていますが有料で広告主(事業者)がそのメディアに出稿料を支払っています。ややこしいですね。。
SNSでも昨年の10月以降、広告・宣伝であることを隠した投稿を罰するステマ規制法が施行され、インフルエンサーが企業などから報酬を得て商品やサービスを宣伝する投稿には広告と分かる表記が義務付けられていますが、その表記にも「#広告」と並んで「#PR」を明記している投稿が多く見受けられます。消費者庁は「広告」とわかるよう明記してね、とガイドしており、「PR」は厳密には「広告」じゃないからNGだよ、とはいっていないので、「#PR」としたからお上からお咎めがあるという訳ではないようですが、このような矛盾も、「PR」という言葉の意味を誤解させている一因ですね。
参考:消費者庁「景品表示法とステルスマーケティング」
6. こんなにある!PRの役割
さて、ここまで読んでくださった方の中には、「パブリック」とか「双方向コミュニケーション」だとかいわれても、さっぱり分からねえ…と思われていることでしょう。
私自身も、「伝える」ことを生業にしていながら、お恥ずかしいことこの上ないのですが、「一言でいいたいのに、いえない(ムズい)」という、誤解も多い職名なだけに、もどかしさを常に感じております。
そこで、ここでPRが手掛ける仕事の種類を一例として上げたいと思います。
これまた「広報部」や「コーポレイト・コミュニケーション部」など、様々な組織名でお仕事されている方々から「それはウチの範疇じゃない」というご指摘があるかもしれませんが、あくまでも私の経験で対応してきたPR業務としてご紹介したいと思います。
今後いつか何かで、「TPRSに相談できるかも?」と思ってもらえたら幸いです。
「社内広報」と「社外広報」
なぜかこの場合はPRではなく「広報」をくっつけて使用するのが慣習になっているのが面白いのですが、企業に「PR(広報)」の部署が設けられている場合、その仕事の多くは「社外」と「社内」で大きく異なります(さらに「攻めの広報」と「守りの広報」で適宜棲み分けたりもします)。大企業になると兼務ではなく以下の各業務に専任の担当者やチームがあります。
「社内広報」
社内報制作(取材・撮影・編集)
CI(コーポレイト・アイデンティティ)の管理
ロゴグッズ企画
社内イベントの企画・運営
「社外広報」
メディアリレーション
プレスリリースの作成・発信
オウンドメディア(自社HPやSNS)での情報発信
取材対応(台本作成とメディアトレーニング)
記者会見の調整と進行
上記のように、「社内広報」は対象が従業員(やその家族も含む)で、「社外広報」はメディア(+メディアを通した世間の人々)やそのほかの社外のステークホルダーとなります。
この両方に共通するのは、その企業(事業)の社会における「存在意義」を正しく理解してもらい、浸透させていくためのコミュニケーション活動です。
社内広報では、これにより従業員の皆さんのモチベーションに繋がったり、社員全員が一貫したメッセージを発信できる優秀なPRパーソンになり得ます。
社外広報では、その「存在意義」が社会のニーズとマッチすると判断して報道してくれるメディアとの出会いに繋がり、事業活動の認知拡大や最適な人材採用のチャンスにもなるのです。
7. PRはなぜ必要なのか?
「PRは事業者とメディア(社会)の架け橋になる」
前述の通り、PR(担当者)はその事業が社会にとって価値あるものであることを伝える役割があります。
商品やサービスを作り、提供する事業者が「これは価値があります。」と主張するのは当然ですよね。PRはメディア側に説得性をもって伝えなければならないため、常に客観的な視点でその「価値」を語る必要があります。なぜならメディアはその商品やサービスが自分たちの読者や視聴者、フォロワーにとって本当に価値があるのか見極める立場にあるからです。
一般の消費者を相手に直接商売をするシーンでの宣伝文句とは事情が異なり、メディアに相対する場合は、そのメディアの先にいる人々(読者や視聴者、フォロワーなど)を見据えた伝え方をする必要があります。
つまり「これは(メディアの読者層である)◯◯のような人たちにとって価値があります。なぜなら〜」と受け手が納得性をもってその情報を受け取ることが重要なのです。そのためには、常にメディアの動向はもちろん、時事を踏まえた社会情勢を把握し、その事業の市場におけるポジションやポテンシャルを俯瞰且つ客観的に捉える能力が求められます。
裏を返せば、社会からその商品やブランド、または会社そのものが、どう見られているかを客観的に事業者に伝えることができるのもPRであり、そこにPR(広報)が介在する価値があると思っています。
「企業(ブランド)価値を上げる」
社会とのより良い関係構築のためには、「攻めのPR」だけでなく「守りのPR」も重要です。特に、炎上といった社会から予期せぬ批判を予防または初期消火するための対策を講じることも「守りのPR」の重要な任務となります。
例えば謝罪対応にしても、ただ闇雲に謝ればいいというものではありません。もし事実誤認がある場合は、しっかり内容に線引きをして説明をするといった、自社の姿勢を正しく伝えることが重要になります。
これは2023年にネットで炎上したスープストックトーキョーの事例が参考になります。
この事例は、スープストックトーキョーの新サービス「離乳食の無料提供」が、ネットを中心に子育て世代を嫌悪するような、難癖も含まれる炎上騒ぎとなった件を受け、スープストックトーキョーが声明文を出したものです。
その内容は安易に謝罪から始まるものではなく、社としての姿勢と新サービスを提供するに至った”想い”を、企業理念を紹介しつつ確固たる姿勢で誠実に示したものでした。この声明がメディアで報道されると、ネットでは非難から一転、称賛に変わったのです。まさに「守り」から「攻め」に転じ、企業(ブランド)価値を上げた好例ではないでしょうか。
このように、事業(商品やサービス)の「情熱」を持ちつつも、「冷静」且つ「客観的」に社会という空気を読んでコミュニケーションを行うPRは、「社会と密接に繋がっていきたい」と考える事業者の方々にとって必要不可欠な活動となります。
参考:株式会社スープストックトーキョー「離乳食提供開始の反響を受けまして」
8. PRを始めるならココがポイント!
PRは事業活動で生まれた商品やサービスを通して、その存在意義を可視化する役目があると思っています。PR活動はその事業活動の根幹(社会における存在意義)を軸に、「誰に」「どんな媒体で」伝えるか、どう伝わったかを検証しつつ、改善しながら地道にコミュニケーションをしていくことが最重要になります。
仮に経営理念もブランドコンセプトもなく、また作った商品をどんな人に食べてもらいたいか(どんな人にサービスを利用してもらいたいか)といった想像さえもせず、「とにかく売上を上げたい」一心のビジネスだった場合、「よっしゃ、いっちょインスタから始めてみよう♪」と場当たり的に発信をしていても、長期的で良好な関係構築にはなり得ません。戦略を立てずに戦術から始めるようなものでしょう。
昨今は「パーパス経営」や「パーパスブランディング」(*2)が声高に叫ばれていますが、
「なぜこの事業をするのか」
「誰の何を解決したいのか」
「この活動を続けることで将来どういう世界を描いているのか」
といった、創業したときの想いや考えを明文化することで、最適なメディアが絞れ、その手段や表現も的確に発信し、コミュニケーションすることが可能になります。
PRを外注するにしても、「インスタはよく分からないからお任せで。」と丸投げではコストが無駄になってしまいかねません。ほかの誰かがPRを代行したとしても、”扇の要”である「経営理念」や「ブランドコンセプト」「パーパス」をしっかり明確化し、それを共有することで、ブレのないコミュニケーションが実現するはずです。
*2:「パーパス」目的、目標などのほかに、ビジネスでは「企業の存在意義」や「事業の目的」を指す
いかがでしたでしょうか?
今回は「PR(広報)」でボリュームを割いてしまったので、「広告」「マーケティング」「ブランディング」については次回以降に解説したいと思います。
「PRは難しい」と思われてしまったかもしれませんが、目的と用法を正しく知れば、皆さんご自身で実践できる、最もコストの掛からない情報発信方法です。
TPRSでは今後、所沢市の事業者や生産者の皆さんが、自分たちでもできるPR方法や、PRに役立つ無料ツールのご紹介もしていきたいと思っていますのでお楽しみに!